「ビリギャルの先生」だけじゃなかった
自分には現在2歳の息子がいる。絶賛子育て中の毎日だ。
子どもが生まれてからというもの、どうしても、育児に関する内容の書籍が目に留まるようになった。
そんな時に知ったのが、この本だ。
本書の著者のことは、以前から知ってはいたものの、正直なところ、「ビリギャルの先生」、というくらいの認識しか持っていなかった。
でも、それはごく限られた一面にすぎず、受験以外の「子どもの教育全般」に関しても、とても示唆に富んだ知見をお持ちの方であることが、本書を読んでよくわかった。
昔聞いた話で、好きな話がある。こんな話だ。
「日本では『人に迷惑をかけてはいけない』と子どもに教えるが、インドでは『あなたも人に迷惑をかけるのだから、人の迷惑も許してあげなさい』と教える」
まさにこの本の内容でもあるし、だからこそ、この本の存在が自分のアンテナに引っかかってきたんだと思う。
珠玉のフレーズたち
(抜き書きの自分用メモのため、一字一句が本文と同一ではありません)
「苦手だね」と言われると、子どもは苦手意識を持ってしまう。
子どもにとっては「自分は算数が苦手だ」という呪いになり、不思議と、それを証明するように思考したり行動したりするようになります。
幼児期に聞いた言葉の数が、子どもの将来を決める。
幼児期の声かけがいかに大切であるか示してくれる良書に『3000万語の格差』があります。簡単に言うと、貧困層の子どもたちが3歳までに聞く言葉の数は、社会的に成功している層の子どもたちと比べて3000万語ほど少ないとする研究です。
言語を吸収して脳が育つ時期に耳が聞こえるようになったとしても、「豊かな言語環境」がなければ、結局、脳が育つことはありません。親や周りの大人が声かけをすることなく、シーンとした場所にいれば、当然ながら言葉を学ぶことができませんよね。
言葉の数が単に多ければいいというわけではありません。社会的に成功している家庭では、豊かな語彙、ポジティブな言葉を使っていたということが研究の結果からわかっています。親がどのような言葉を使うかによって、子どもの将来を左右すると言っても過言ではありません。
僕は娘に「You’re my treasure.(あなたは僕の宝物だよ)」と毎日伝えています。子どもに、「自分には価値がある」と感じてもらうこと。これをとても大切にしています。自分の存在に価値があると思えたら、「私はこう思う」と意見を言えるようになります。
誰にも迷惑をかけず、誰の手も借りずに生きている人なんていない。それなら、「人に迷惑をかけて助けてもらった分、誰かにお返ししていこう」と考える方が健全です。
「迷惑をかけるな」と子どもに教える国は、日本くらい。
子どもは社会の宝です。いくら「自分には子どもはいない」「子どもは嫌い」と言っても、将来の社会を支えてくれるのは今の子どもたちです。「誰の世話にもならない」なんて無理な話で、年金だって働いている世代が払っているお金から支給されます。
それでも、どうしても迷惑そうにする人はいます。その人自身が「迷惑をかけてはいけない」呪いにかかっていて自己肯定感も低く、他人を攻撃しがちなのでしょう。そういう一部の人たちに合わせる必要はありません。
レストランで子どもが走り回っていたら、「走っちゃダメ!迷惑でしょ」と言うのではなく、「周りの人をハッピーにさせてごらん」と言ってみてはどうでしょうか。
失敗こそ、学びのチャンスです。そして、失敗を乗り越えるほどに、失敗に対する耐性も身につきます。子どもの頃にたくさんの失敗をさせてあげた方がいいのです。
「母は何でも失敗させてくれる人でした」
(ユーグレナ社長・出雲充)
僕も出雲さんのお母さんを見習って、娘に対して見守る姿勢でいるよう努力しています。「これはやばいな、死ぬな」というもの以外は止めない。例えばバカラの店でグラスを割る失敗をしても、弁償する!という覚悟でいます。
ほとんどの親は、子どものことをBeingで愛しています。たとえDoingもHavingも最悪だったとしても、心の底で存在そのものを肯定しています。ところが、言葉にするのはDoingとHavingの評価ばかり。
社会では嫌でもDoingとHavingで評価されるのですから、親くらいはBeingで評価することが重要なんです。
僕は塾で初めて会う子どもたちによく「プラチナカード」というのを書いてもらいます。今、神様が目の前に現れて、キラキラ輝くカードをくれたとします。そこに書いたことは何でも叶います。君はなんて書く?というものです。その子に「こういうことをしたい」「これが好き」というものを聞いて、その本質的な部分を見据えて「じゃあ、こうなったら最高だよね」と最上級バージョンを提示できたら、子どもの目はイヤでも輝きます。
「カルピスちょうだい」に対するイエス/ノーで答えようとするのではなく、「喉が渇いたの?」とか「つまらなかった?」など、その子の言いたいことを探る問いを1つでも入れることが重要です。
日本の親はもっと子どもに仕事の話をした方がいいと思っています。
ことあるごとに大人たちからほめられている子は、自分に自信を持てるようになるし、他人をほめることも素直にできるようになるでしょう。
「共感」はとても大切です。共感しながら話を聞いていれば、子どもは何でも話してくれるようになります。
多くの場合、共感よりダメ出しが多いから話さなくなるのです。ダメ出しされないためには、情報をあまり出さない方がいい。だから話さなくなるのです。
スマホやゲームを与える時には、子どもと一緒にルールを作りましょう。少し前に、現Linkedin日本代表の村上臣さんが、中学1年生の息子さんに渡した「誓約書兼スマートフォン貸与契約書」がネット上で話題となりました。
3歳までは難しいかもしれませんが、基本的には言葉がしっかりしてきたらルール作りを一緒にやるのがいいと思います。例えば「ジュースを飲みたい」と子どもが言ったら「じゃあ、ジュースは1日何杯までにしようか?何杯までならいいと思う?」というところから話していきます。
「ルールは守るもの」というより「ルールは作るもの」という感覚が身につくのがまたいいところです。
「ルールだから守る」と思考停止になってしまうのではなく、ルールを変える・作ることができるというのは、これからの時代に必要な能力の一つです。
「やればできる!」という声かけは、多用するとやる気がなくなります。チャレンジしなくなります。なぜなら、本当にやってみてできなかったら、それは自分の能力がないことを証明することになるからです。
「片づけなさい」は、小さいうちはNGです。「片づける」という言葉がどういうことを指しているのかわかりにくいからです。「元あった場所に戻そうね」「この写真の通りに置いてね」と言う。
「ちゃんとしなさい」。言いがちですが、「片づけなさい!」以上に、よくわからない言葉です。
伝え方のポイントは、アイメッセージです。
国や文化によって常識はいくらでも変わるわけですから、親の思う「当たり前」を子どもに身につけさせたところで、世界では通用しないと思った方がいいのです。
信頼できる仲間になるために、自分は子どもにどうやって接してきたかなと振り返り、今後はどうやっていこうかと考える。それこそが大事な観点だと思います。
あとがき
子育てをしていると、「こちらが相手を育てているようで、実は自分の方が育てられている」、と感じることがよくある。
「子育てのために読んだ本が、それ以外の面でも自分を成長させる学びになった」、というのもその一つだろう。
これからも子どもと一緒に成長していきたい、そう思わせてもらえた一冊です。
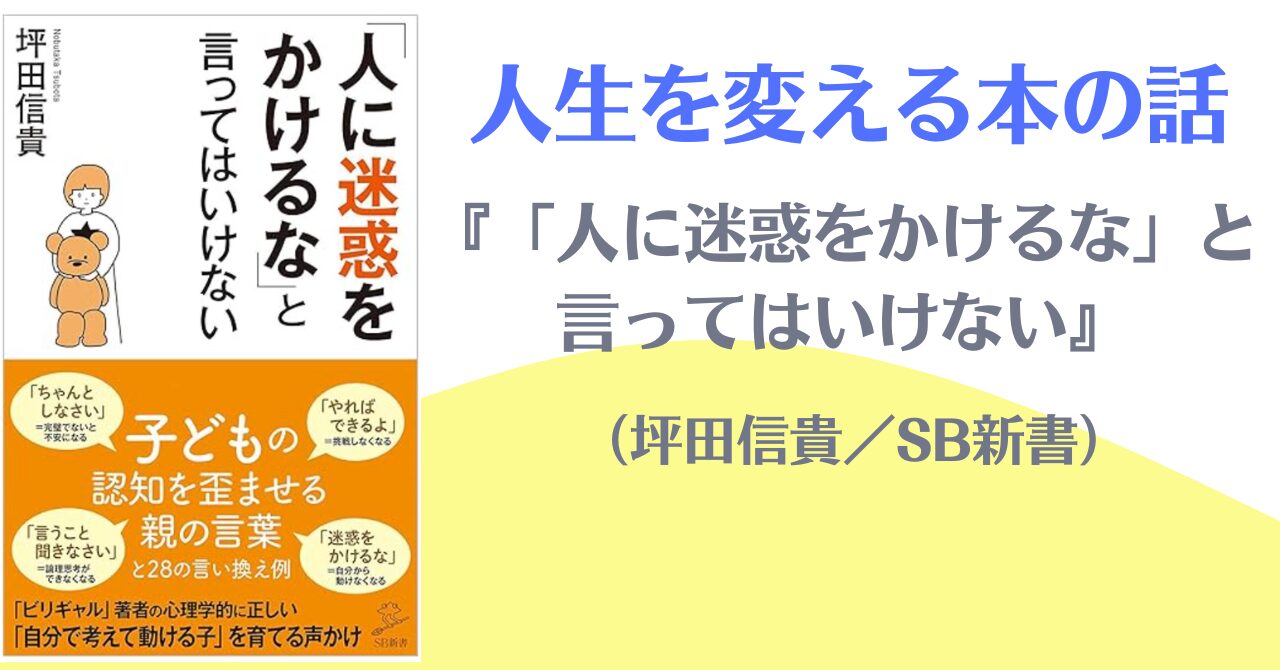
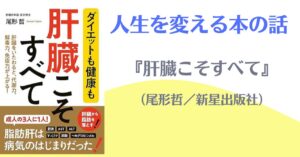
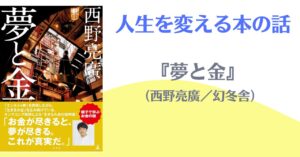
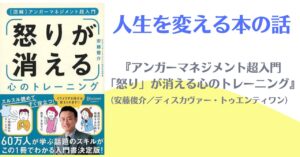
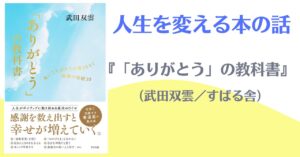

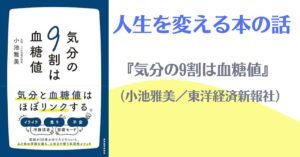
コメント